こんにちは!現役薬剤師のおちょおまんです。
インフルエンザシーズン、「イナビル吸入粉末剤」と「リレンザ」の処方が連続で来た…! 新人薬剤師の皆さん、こんな場面で悩んでいませんか?
- 「どっちも吸入薬だけど、どう使い分けるのが正解?」
- 「1回で終わるイナビルと、5日間続けるリレンザ。患者さんにはどっちが良いんだろう?」
この記事では、「アドヒアランス(服薬・吸入の遵守)」と「手技の確実性」という実践的な観点から、イナビルとリレンザ、そして他の抗インフルエンザ薬について徹底的に掘り下げます。
【最重要】イナビル vs リレンザ 最大の違いは「アドヒアランス」
この2剤の使い分けの核心は、「1回で確実に治療を終えるメリット」と「5日間かけてでも確実に投与するメリット」のトレードオフです。

薬局長!インフルエンザの患者さんが来たのだ。
イナビルをサクッと吸うよう説明したのだ!
1回で終わるから最強なのだ!
5日間も吸わなきゃいけないリレンザを
あえて選ぶ理由がわからないのだ。

あー、新人あるあるだわ。
確かにイナビルは『吸入忘れ』が絶対にないのが最強のメリット。
でもね、その『1回』で吸入ミスったらどうなる?

えっ…効果ゼロなのだ…?

そゆこと。
そのリスクをどう評価するかが薬剤師の腕の見せ所っしょ。
イナビル(ラニナミビル):単回投与の「利便性」と「失敗リスク」
- 最大のメリット(処方意図): 単回吸入で治療が完結します。5日間継続が難しい患者(例:多忙な社会人、薬を忘れがちな人)にとって、アドヒアランス遵守の観点から最強の選択肢です。
- 最大のデメリット(指導時の注意点): 治療が「その1回」に懸かっています。もし患者さんが手技をうまくできず、薬剤を十分に吸入できなかった場合、治療失敗に直結します。
- 疑義照会ライン: 処方理由は理解できるが、患者さんが明らかに手技を理解できていない、または吸入が困難そう(例:幼すぎる小児、手先の不自由な高齢者)な場合。「1回で終わる」というメリットよりも、「1回を失敗する」デメリットが上回ると判断したら、他剤への変更を検討すべきです。
リレンザ(ザナミビル):5日間投与の「手間」と「確実性」
- 最大のメリット(処方意図): 1日2回・5日間(全10回吸入)という用法が、逆に「手技失敗のリスク分散」になります。万が一、1~2回の吸入がうまくできなくても、残りの吸入で治療効果を担保しやすいです。医師が「イナビル単回はリスクが高い」と判断した患者に選択されます。
- 最大のデメリット(指導時の注意点): 5日間のアドヒアランス維持が課題です。インフルエンザの症状は通常2~3日で急速に改善するため、患者さんが「治った」と自己判断し、途中で吸入を中断してしまうリスク(=耐性ウイルスの原因)を伴います。
- 指導のポイント: 「症状が消えても、ウイルスはまだ体内にいます。5日間しっかり使い切ることが重要です」と、アドヒアランス中断のリスクを潰す指導が必須です。
処方意図を読む!経口薬・注射薬との比較
吸入薬が処方されていない場合、その理由(処方意図)を考えます。
経口薬(タミフル・ゾフルーザ)
吸入デバイスの使用自体が困難な場合の第一選択です。ここでも「5日間 vs 1回」の比較になります。
- タミフル(オセルタミビル)
- 5日間投与。使用実績が圧倒的に長く、DS(ドライシロップ)もあるため小児への処方意図は明確。リレンザ同様、アドヒアランス維持の指導が重要。
- ゾフルーザ(バロキサビル)
- 単回投与。イナビルと同様、アドヒアランスを最優先する場合(例:薬を飲み忘れそうな一人暮らしの高齢者、5日間の服用を嫌がる学童など)に処方される。
- 薬剤師の留意点:耐性ウイルスの出現頻度が他剤より高いとされる。特に小児への処方では、そのリスクも念頭に置く。
注射薬(ラピアクタ)
- ラピアクタ(ペラミビル)
- 経口・吸入が不可能な患者(嘔吐が激しい、意識障害、入院管理中の重症例)への処方。処方意図は最も明確。
【薬剤師向け】患者説明・質問対応テンプレ
新人薬剤師が患者さんからの質問で詰まりがちなトピックをまとめます。
Q1.「熱がぶり返した!薬が効いてない!」
- A.(二峰性発熱の説明)
- 「インフルエンザでは、『二峰性発熱(にほうせいはつねつ)』といって、一度熱が下がりかけた後に再び上がることがあります。特に小児に多い現象です。」
- 「薬はウイルスの増殖を抑えるもので、熱を直接下げる解熱剤とは異なります。多くは自然な経過ですが、呼吸が苦しいなど他の症状が強ければ、肺炎などの合併症も考えられるため再受診を勧めてください。」
Q2.「タミフルの異常行動が怖いんですが…」
- A.(因果関係の説明)
- 「以前報道がありましたが、その後の調査で『タミフルと異常行動の明確な因果関係は確認されていない』というのが現在の見解です。」
- 「インフルエンザ自体が、高熱に伴う『熱せん妄』や『インフルエンザ脳症』を引き起こし、異常行動の原因となることが分かっています。」
- 「ですので、タミフルを飲んでいなくても異常行動は起こり得ます。発症から2日間は、念のためお子さんを一人にしないよう見守ってあげてください。」
【薬局実務】耐性ウイルスの現状
耐性ウイルスの問題(アマンタジンの歴史)

耐性ウイルスってそんなにやばいのだ?

ヤバいよ。昔『アマンタジン(シンメトレル)』ってA型インフルに効く薬があったんだけど、今じゃほぼ100%耐性化しちゃって、全く使い物にならないわけ。薬が一個ムダになったのと同じ。
- 歴史的教訓(アマンタジン)
- かつてA型インフルエンザ治療薬としてアマンタジン(シンメトレル)が使われていました。
- しかし、現在流通しているA型インフルエンザウイルスは、ほぼ100%がアマンタジン耐性を獲得しています。
- このため、アマンタジンはインフルエンザ治療薬としての推奨から外れ、現在は使用されません(パーキンソン病治療薬としてのみ使用)。耐性化によって一つの治療選択肢が完全に失われた典型例です。
コラム:海外で抗インフルエンザ薬を使わない理由
- 患者さんから「海外では薬なんか飲まないって聞いた」と言われることがあります。
- 回答例:「アメリカなどでは、健康な成人は自己免疫力で治す『対症療法(解熱剤など)』が基本です。抗ウイルス薬は発熱期間を1日程度短縮する効果がメインと捉えられているためです。ただ、日本は医療アクセスが良く、国民皆保険のもと安価に薬が使えるため、重症化予防も兼ねて積極的に使う傾向にあります。」
【まとめ】
インフルエンザ治療薬の選択は、アドヒアランスと確実性のトレードオフです。
- イナビル(単回):アドヒアランスは完璧だが、手技失敗のリスクを伴う。
- リレンザ(5日):手技失敗のリスクは低いが、アドヒアランス中断のリスクを伴う。
- 経口薬:吸入が困難な患者の選択肢。ここでも「単回(ゾフルーザ)」か「5日(タミフル)」かのトレードオフがある。
- 耐性化のリスク:アマンタジンの歴史を教訓に、適正使用(特に5日間製剤の使い切り指導)を推進する。
イナビルの処方せんが来たら「この患者さんは1回で確実に吸入できるか?」を、リレンザやタミフルの処方せんが来たら「この患者さんは5日間しっかり使い切れるか?」をアセスメントする癖をつけましょう。
【参考文献】
https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00006619.pdf
イナビルインタビューフォーム
https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00002742.pdf
リレンザインタビューフォーム
https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00000782.pdf
タミフルインタビューフォーム
https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00007183.pdf
ゾフルーザインタビューフォーム
https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00006812.pdf
ラピアクタインタビューフォームhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/115/7/115_663/_pdf
インフルエンザウイルスの薬剤耐性
https://www.kansensho.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=37
日本感染症学会 提言「抗インフルエンザ薬の使用について」
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/matsumoto/201511/544353.html
インフルエンザの2峰性の発熱
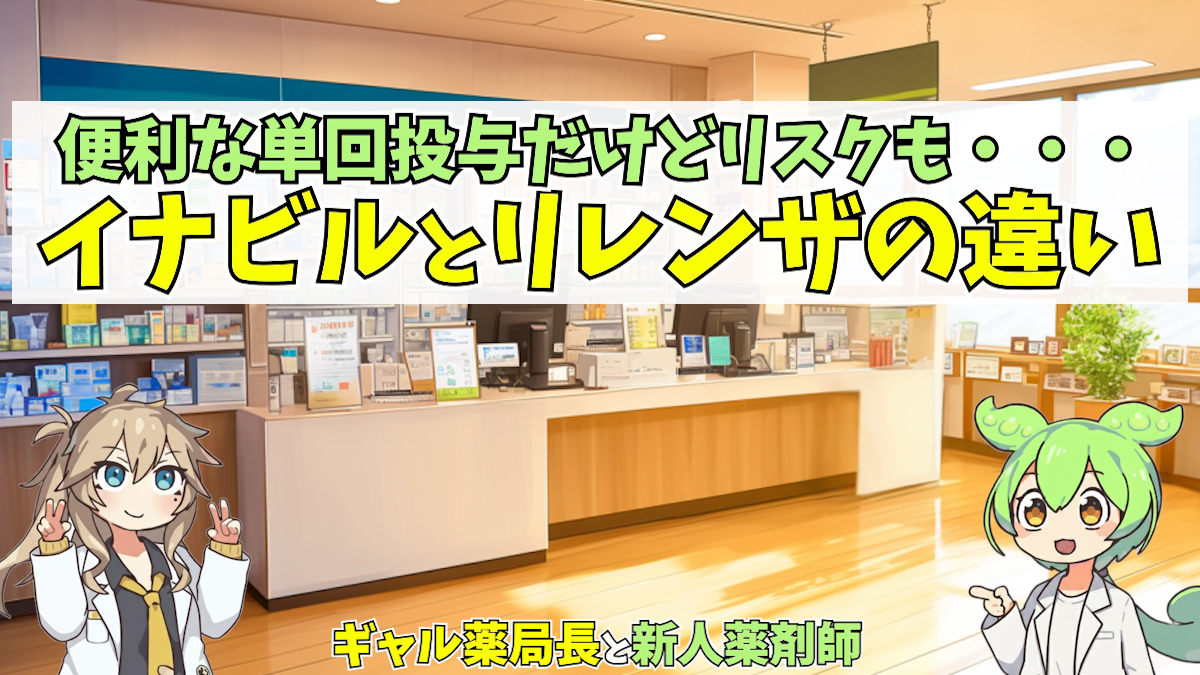


コメント