こんにちは!薬剤師のおちょおマンです。 このブログは、薬局現場で奮闘する若手薬剤師の皆さんに向けて、日々の業務に役立つ知識を発信しています。(YouTubeでも解説しているので、ぜひチェックしてください!)
さて、今日のテーマは「ビスホスホネート製剤(BP製剤)」です。

薬局長!ビスホスホネート製剤って、なんでこんなに種類が多いのだ?

週1回(Weekly)とか月1回(Monthly)とか、おまけに静注まであって、患者さんに説明するとき混乱するのだ…。

あー、BP製剤の規格と剤形ね。同じ成分で投与間隔変わるからビビるよねー。

そうなのだ!あと、プレドニン飲んでる人にも出てるし、顎骨壊死(MRONJ)とか怖い副作用もあるし…。全部まとめて理解したいのだ!
BP製剤は骨粗鬆症治療の第一選択薬でありながら、服薬方法が極めて特殊で、副作用管理も重要な薬剤です。 今回は、BP製剤の「投与間隔と規格」をメインテーマに据えつつ、現場で必要な関連知識(小ネタ)も網羅的に解説していきます!
なぜBP製剤の投与間隔はこんなに多様なのか?

ずんだもん、そもそもなんでDaily(毎日)製剤が主流じゃなくなったと思う?

あの複雑な飲み方を毎日続けるのが大変だからなのだ?

大正解!BP製剤って極端に吸収率が低いし(約1%未満)、CaとかMgとキレート作ってすぐ吸収されなくなるの。

だからあの厳密な服薬ルールが必要なんだけど、アドヒアランスがめちゃくちゃ悪かったわけ。
BP製剤の歴史は、アドヒアランス向上との戦いでした。 Daily製剤の服薬コンプライアンスの低さを改善するため、半減期が長く骨に蓄積しやすい特性を活かし、Weekly製剤が開発されました。その後、さらにアドヒアランスを高めるためにMonthly製剤、さらには医療機関で投与が完結する静注(IV)製剤が登場したのです。
【投与間隔別】BP製剤の規格一覧と指導ポイント
剤形選択の基本は「アドヒアランス」。患者さんのライフスタイルや服薬管理能力に合わせて、医師が最適な剤形を選択します。
Weekly製剤(週1回)
最もスタンダードな剤形です。「週1回、起床時」に服用します。
主な薬剤
・アレンドロン酸(フォサマック35mg, ボナロン35mg)
・リセドロン酸(アクトネル17.5mg, ベネット17.5mg)
指導ポイント: 飲み方に注意が必要です、「起床時・水で飲む・30分横にならない・水以外の飲食を避ける」
Monthly製剤(月1回)
Weekly製剤の服用も困難、または負担に感じる患者さん向けです。「月1回、起床時」に服用します。
主な薬剤
・リセドロン酸(アクトネル75mg、ベネット75mg)
・ミノドロン酸(ボノテオ50mg、リカルボン50mg)
・イバンドロン酸(ボンビバ100mg)
指導ポイント: Weekly製剤と同様の服用方法。月1回なので、カレンダーに印をつけてもらうなど、飲み忘れ防止の工夫がより重要になります。
Daily製剤(毎日1回)
BP製剤の最も初期の剤形です。「毎日」服用します。
主な薬剤
・アレンドロン酸(フォサマック5mg, ボナロン5mg)
・リセドロン酸(アクトネル2.5mg, ベネット2.5mg)
・ミノドロン酸(ボノテオ1mg, リカルボン1mg)
指導ポイント:「起床時・水で飲む・30分横にならない・水以外の飲食を避ける」という厳格な服薬ルールを「毎日」継続する必要があります。 アドヒアランスの維持が非常に困難であるため、現在ではWeekly製剤やMonthly製剤の登場により、処方される頻度は減少傾向にあります。
静注(IV)製剤
経口服用が困難な患者(嚥下困難、消化器潰瘍リスク、服薬管理が困難など)に用いられます。
主な薬剤
・イバンドロン酸(ボンビバ 1mg / 4週に1回)
・ゾレドロン酸(リクラスト5mg / 1年に1回)
指導ポイント: 医療機関で投与が完結するため、薬剤師が直接投与に関わることは少ないですが、他剤からの切り替え時(特に経口BPからの休薬期間)や、お薬手帳での副作用モニタリング(特に急性期反応:発熱、倦怠感など)で関わります。
若手薬剤師必見!BP製剤の+α
ここからは、BP製剤を扱う上で「これも知っておきたい!」という関連知識をいくつかご紹介します。
+α①:なぜ「朝イチ・水で飲む・30分横にならない・水以外の飲食を避ける」必要がある?
これはBP製剤の服薬指導で最も重要なポイントです。
- なぜ「朝イチ(起床時・空腹時)」?
- 食事(特に牛乳などのCa・Mg含有食品)と同時摂取すると、キレートを形成し吸収率がほぼゼロになるため。
- なぜ「水(硬度の低い水)」?
- 牛乳、お茶、ジュース、ミネラルウォーター(硬水)に含まれるCa, Mg, Feなどとキレートを形成するため。コップ1杯(約180mL)の水で服用します。
- なぜ「服用後30分(ボンビバは60分)飲食禁止」?
- 上記1, 2と同じ理由で、腸管からの吸収を担保するため。
- なぜ「すぐに横にならない(立位・座位)」?
- BP製剤は食道粘膜への刺激性が非常に強い薬剤です。食道に停滞・逆流すると、食道炎、潰瘍、重篤な場合は穿孔を引き起こすリスクがあるため。
+α②:プレドニン(ステロイド)の副作用予防で使うのはなぜ?

プレドニンを長期で飲んでる患者さんにも、BP製剤が出てるのをよく見るのだ。

それ!『ステロイド性骨粗鬆症』の予防・治療だね。ステロイドは骨吸収を促進し、骨形成を抑制するから、骨がめちゃくちゃ脆くなるの。
ステロイドの長期投与は、骨折リスクを著しく高めます(ステロイド性骨粗鬆症)。 この予防・治療の第一選択薬として、アレンドロネート(ボナロン・フォサマック)およびリセドロネート(アクトネル・ベネット)が第1選択薬としてガイドラインで推奨されています。
+α③:最重要副作用「MRONJ(薬剤関連顎骨壊死)」
MRONJ (Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw) は、BP製剤やデノスマブ(プラリア)で報告される重篤な副作用です。
- 症状:顎の痛み、腫れ、歯のぐらつきなど。
- リスク因子:抜歯などの侵襲的な歯科治療、長期投与、口腔内不衛生など。
薬剤師の役割: BP製剤の開始前・投与中は、必ず「歯科治療(特に抜歯)の予定がないか」を確認すること。 予定がある場合は、投与開始前に歯科治療を終えるよう医師・患者に促します。投与中に抜歯が必要になった場合は、処方医と歯科医の連携が必須です(休薬の要否を検討)。
+α④:見逃すな「AFF(非定型大腿骨骨折)」
MRONJほど頻度は高くありませんが、AFF (Atypical Femoral Fracture) も重篤な副作用です。
- 特徴:非常に弱い力(または外傷なし)で大腿骨(太ももの骨)を骨折する。
- リスク因子:BP製剤の長期投与。
- 前駆症状:骨折の数週間~数ヶ月前から、大腿部や鼠径部(股関節)に鈍い痛みを感じることがある。
薬剤師の役割: 長期服用患者へのモニタリングが重要です。 「最近、太ももや股関節あたりに原因不明の痛みはありませんか?」と一声かけることで、AFFの前駆症状をキャッチできる可能性があります。
+α⑤:「ドラッグホリデー(休薬期間)」の考え方
BP製剤は骨に蓄積するため、長期(3-5年程度)継続した後は、一旦休薬(ドラッグホリデー)を設けることが推奨されています。

AFFのリスクは長期投与で上がるからね。メリットとデメリットを天秤にかけて、医師が休薬を判断するわけ。
休薬中は定期的に骨密度を測定し、骨密度が低下したり新たな骨折が起きた場合は、再開を検討します。
ビスホスホネート製剤【まとめ】
今回は、ビスホスホネート製剤の多様な「規格と投与間隔」を中心に、若手薬剤師が押さえておくべき関連知識を網羅的に解説しました。
- BP製剤の多様な剤形は、アドヒアランス向上のために開発された。
- 同じ成分でも規格により投与スケジュールが異なるので過誤に注意。
- 服薬指導では「起床時・水で飲む・30分横にならない・水以外の飲食を避ける」理由をセットで説明する。
- 重篤な副作用(MRONJ・AFF)のモニタリングが薬剤師の重要な役割。
BP製剤は、薬剤師の薬学的知見とコミュニケーション能力が最も試される薬剤の一つです。ぜひ明日の服薬指導に活かしてください。
参考資料
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版
https://jsbmr.umin.jp/pdf/GL2015.pdf
ステロイド製骨粗鬆用の管理と治療
https://jsbmr.umin.jp/guide/pdf/gioguideline.pdf
薬剤関連顎骨壊死の病態と管理:顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023
https://www.jsoms.or.jp/medical/pdf/2023/0217_1.pdf
ファーマスタイルWEB:専門医+エキスパートに聞く(骨粗鬆症)
https://credentials.jp/2019-05/expert-1905/
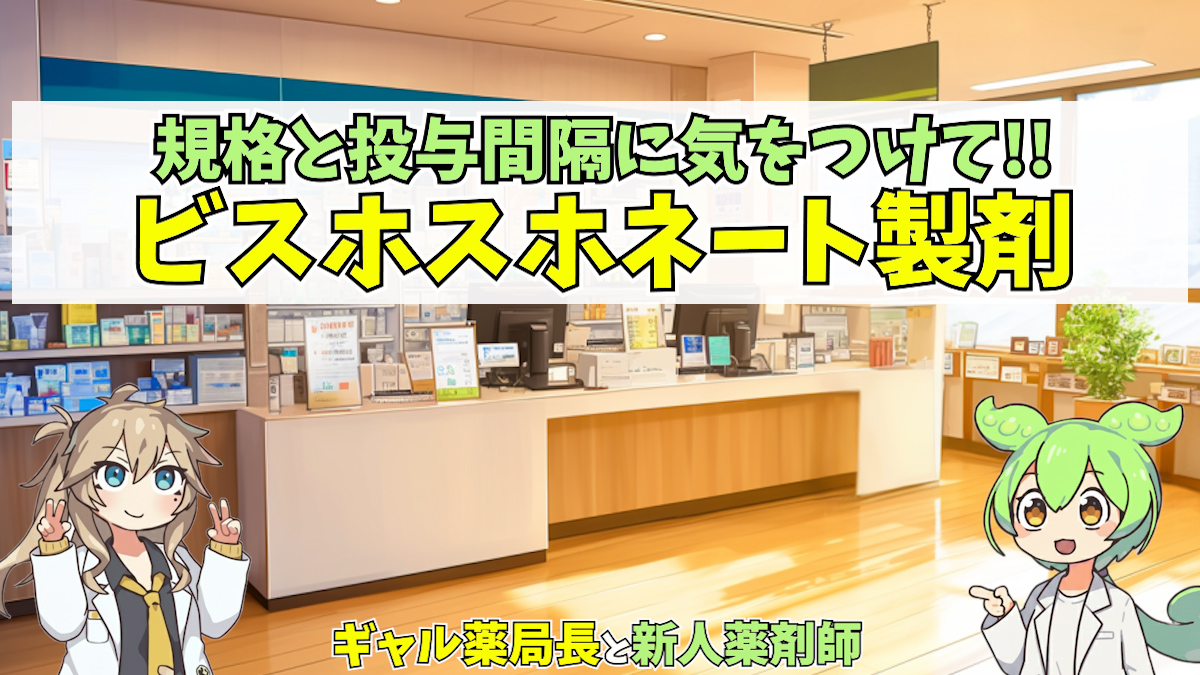


コメント